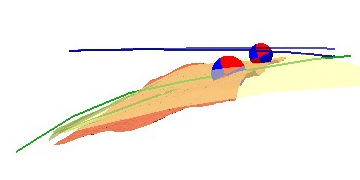
2011年東北地方太平洋沖地震の断層面を探る |
|---|
| 戻る |
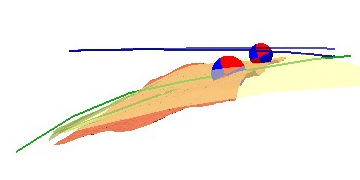
|
メカニズム解によってズレ動いた断層面の候補(節面)の走向、傾き、すべり角などの情報が明らかにされています。
個別地震の震源断層パラメータから類似スペックのデータを抽出してグループ(群)のスペックとして情報化し、
断層の存在や断層面の3次元形状を探ってみます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類似スペックの震源断層面に注目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
類似スペックの震源断層面が重なるとき、共通の断層が存在する可能性があります。重なるデータが多いほど、断層が存在する可能性は高くなります。 また、ある震源断層面の延長に類似スペックの震源断層面が遠くない距離にあるとき、つながっているか否かは不明ですが、なんらかの関係をもつ断層が存在する可能性があります。 ここでは、震源断層パラメータデータを処理していく上で、次のふたつを前提としています。 1)余震や前震は本震の断層面に沿って発生する傾向がある。 余震や前震データを断層面の推定に使用します。 2)M6以上の地震は既存の断層が関与している。 断層が存在するところは地殻が脆弱で、地殻の破壊が進行しやすい。 2011年東北地方太平洋沖地震のように長さ約450km、幅約200kmと破壊領域が広大な場合、既存の断層が多く関与していると考えます。 そこで、日本海溝以西の東北沖および関東沖で発生したデータも使用していきます。 以下、2011年東北地方太平洋沖地震を3・11M9.0本震、2011年3月9日M7.3地震を3・9M7.3前震ということにします。 防災科研(防災科学技術研究所)の初動解パラメータ・データ(「F-net 地震のメカニズム情報」)を使用します。 震源断層面の重なりと延長 図1には2011年3月9日から10日にかけて発生した類似スペックの地震4個を描いています(スペックは表1に掲載。単位は省略しています。以下、同じ。)。 震源断層面の重なり状態から共通の断層面を想定することができ、3・9M7.3前震と3・11M9.0本震をつなぐ断層と考えます。 図2には2003年から2008年にかけての類似スペックの地震データ(表2参照)を追加して描画しました。 この断層は3・9M7.3前震から3・11M9.0本震の破壊過程で新しくつくられたのではなく、2011年以前にも存在していたと考えられます。 図3は、3・11M9.0本震の南側で、2002年から2008年にかけて発生した類似スペックの地震(表3参照)を描画したものです。 ここでも震源断層の重なりが見られ、共通の断層を想定することができます。 図4は、図1の地震データと図3の地震データを合わせて描画したものです。真上から見た図では、東西方向では震源断層面の重なりが見られますが、南北方向では重なっていません。 しかし、サイドから見た図では傾きがほぼ同じで、震源断層面を南北方向に延ばすと、延長先でほぼ重なります。 地震データから計算した矩形(中心:北緯38.05°、東経142.99°、深さ24km、走向200°、傾き24°。長さと幅は対象地震を囲む範囲で設定)を描画してみると、 サイドから見た図では矩形沿いに大きくずれることなく震源断層面が並んでいます。この矩形を仮想断層面として扱っていきます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 類似スペックのデータを集める | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
震源断層パラメータが類似したデータ集団を震源断層群、類似スペック抽出の元になる地震データをMain地震、
抽出した地震データをTarget地震と呼ぶことにします。 Target地震がMain地震の震源断層面に沿ってどのように分布しているかを調べ、分布の広がりを表す矩体(直方体)を求めます。 この矩体に分布するデータの様子から震源断層群の断層面を推定します。 矩体を震源断層群のBody、推定した断層面を仮想断層面と呼ぶことにします。 震源断層群のBodyや仮想断層面は、地震型、位置(緯度、経度、深さ)、長さ、幅、走向、傾きなどの情報をもちます。 Bodyには高さ情報があり、現在10kmで固定しています。 位置情報はMain地震の震源位置を使用し、走向、傾き情報も基本的にはMain地震の情報を参照します。 Target地震の分布から長さ・幅を設定します。 Main地震のMagが大きくてもTarget地震の分布が狭いと、長さ・幅は小さくなります。 逆にMain地震のMagが小さくてもTarget地震の分布が広いと、長さ・幅は大きくなります。 通常、仮想断層面の位置はBodyの高さ中点にとります。 図5は、3・11 M9.0本震(震源周辺)の震源断層群を描画したものです。点線はBodyの輪郭です。 抽出したTarget地震の主なデータを表4に掲載します。 3・11M9.0本震の震源断層面は、走向 200°, 傾き 27°, すべり角 88°です。 震源断層群のBody情報は、位置(北緯38.1035°、東経142.8610°、深さ23km)、長さ 110km、幅 80km、高さ 10km、走向 200°、傾き 23°としました。 ※傾きについて 3・11M9.0本震のスペックでは傾きは27°ですが、Bodyの傾きはTarget地震の平均値 23°にしています。 因みに、Target地震の走向の平均値は199°ですが、3・11M9.0本震のスペック200°のままにしています。
[震源断層群の求め方] 日本海溝以西の東北沖・関東沖で発生したM5.0以上の地震をMain地震とし、 メイン地震の震源周辺(緯度+-0.45°、経度+-0.45°)に発生した地震の中からTarget地震を抽出します。 ※類似スペックの範囲:今回は、3・11 M9.0本震(震源周辺)の震源断層群の類似データの中に3・9 M7.3前震が含まれる条件を類似スペックの範囲としています。 Target地震としてマッチするかのチェック項目は、以下の通りです。 ●地震情報のチェック 逆断層、正断層、横ずれ断層(左横ずれ、右横ずれ) ※2007年M6.8中越沖地震のように、震源断層面を2枚もつタイプは除きます。 ●P軸、T軸情報のチェック 軸ベクトルを水平方向、垂直方向に分解します。Main地震が 逆断層の場合、P軸が水平方向に卓越することから、P軸ベクトルの走向、傾きを比較。 走向はMain地震の+-20°以内、傾きは+-15°以内ならOKとしました。 ●スリップベクトルのチェック スリップベクトルを水平方向と垂直方向に分解して、走向、傾きを比較 走向はMain地震の+-20°以内、傾きは+-15°以内ならOKとしました。 ●Main地震の震源断層面とTarget地震の震源断層面の近接性チェック 「近接性」のチェック方法はいろいろ考えられますが、ここでは次のように処理しました。 Main地震とTarget地震の震源断層面の矩形を求め、矩形の法線から、2つの矩形のなす角度を求めます。 さらに、Target地震の震源とMain地震の矩形との距離(Target地震の位置からMain地震の矩形に下した垂線の足の長さ)を求めます。 2つの矩形のなす角度の差は+-20°以内、Target地震の震源とMain地震の矩形との距離は20km以内ならOKとしました。 以上、すべて満たすデータをTarget地震としました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| つなぎ合わせる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ふたつの震源断層群AとBの仮想断層面が連結可能かを考えてみます。 1)AとBは、地震型、走向、傾きなどのスペックが類似している必要があります。(サイズは類似していなくてもかまわない。) 2)ふたつの仮想断層面は重なったり、あるいは、遠くない距離内で仮想断層面の延長にある必要があります。 計算で処理するために、AのBodyを拡張してBの仮想断層面(矩形)が拡張Body(直方体)の中に一部でも含まれるかチェックします。 3)Aの拡張Bodyの中にBのTarget地震(Bを構成する地震データ)が一部でも含まれるかチェックします。 以上の3条件を満たすとき、AからBに連結可能とします。 AからBに連結可能でも、BからAには連結可能でないケースがあります。どちらからでも連結可能なとき双方向連結、片方からのみのとき単方向連結と呼ぶことにします。 ※AのBody(拡張していないBody)内で発生した地震の余震がBのBody内にまで分布していれば、仮想断層面がつながっている有力な情報になります。 2つの震源断層群が上記の連結条件を満たすとき直接連結、直接連結はできないが、他の震源断層群を介して連結する場合、間接連結と呼びます。 介する震源断層群を連結Keyと呼びます。連結Keyは連結元や連結先とは直接連結している必要があります。 連結Keyと類似スペックの震源断層群が他にもあれば、連結Keyは一意に定まりません。連結Keyが一意に定まらないときは、双方向連結の震源断層群があれば、それを優先します。 遠く離れた震源断層群が連結するには、連結Keyが複数必要になります。 図6は、3・11 M9.0本震(震源周辺)と直接連結する震源断層群の例、図7は、間接連結する震源断層群の例です。表5にはスペックを掲載しています。
仮想断層面の深さの計算、平滑化処理 図8は、3・11 M9.0本震(震源周辺)に連結する各震源断層群の仮想断層面をメッシュ分割して各点の深さを計算し、 3・11 M9.0本震の仮想断層面の3次元形状を描画したものです。 ※日本海溝沿いのエリアでは、3・9 M7.3前震周辺を除き、M5以上の逆断層型地震の初動解データが少なく、 仮想断層面の深さ情報を得られませんでした。 震源断層群の仮想断層面は矩形で表していますので、使用できるデータが少ないと、 上端ブロック部分と下端ブロック部分が近くにあると段差状になってしまいます。 なるべく各震源断層群の仮想断層面が重なるようにピックアップして深さを平均計算し、不自然な高低差を平滑化しました。 図では、岩手沖にある高まり(陸地側)と凹み(日本海溝側)、福島沖の凹み(日本海溝側)が目立ちます。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 仮想断層面沿いの地震 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
図9は、3・11 M9.0本震の仮想断層面沿いに発生した地震を描画したものです。
2011年から2015年までに発生した地震を赤色で、
過去に発生した地震で、初動解データが存在する1998年から 2010年までの地震を青色、
それ以前の初動解データがない地震を灰色で描いています。
[使用したデータ] メカニズム解データは、防災科学技術研究所の「F-net 地震のメカニズム情報」を使用(1997年-2019年3月)。 ※海底面の深さデータは、日本海洋データセンターが公開している「500mメッシュ水深データ」を使用。 ※太平洋プレートの沈み込みデータは、 Fuyuki Hirose's HP で公開されている数値データを使用。 Kita et al. (2010, EPSL)およびNakajima and Hasegawa (2006, GRL)、 Nakajima and Hasegawa (2006, GRL)、弘瀬・他 (2008, 地震)、Nakajima et al. (2009, JGR) ※海域の活断層ラインは、「日本の活断層図」(活断層研究会編、東京大学出版会)に収録されている地図から読み取ったデータを使用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||